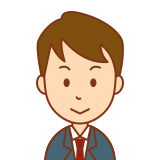
散瞳検査を受けました。
散瞳検査
散瞳検査は眼の検査のひとつで目薬を使って瞳(瞳孔)を開く検査です。
眼の奥をしっかり確認したい時によく行われるそうです。

散瞳検査について詳しくは眼科医の解説へ
散瞳検査の受け方
散瞳検査を実施するかどうかは眼科医の判断になります。
ただ、健康診断等で明らかに異常の可能性を指摘された場合は、初診で検査を実施することもあります。
このあたりは症状に応じてという事です。
まずは検査を受ける眼科を決めましょう。

眼科医探し
現在、通院している眼科があれば、そこで相談するのが良いと思います。
かかりつけの眼科が無い場合は新規で探す必要があります。
探す際のポイントは、
・検査設備のある眼科
・公共交通機関から近い
といったところです。

検査設備に関してはネットを調べれば大抵出てきます。
また、検査後は車等の運転が出来ませんので公共交通機関から近い方が良いです。
持っていくもの
症状により、初診の後いきなり散瞳検査をする事もあります。
初診であっても準備はしておく方が良いです。
持っていくものには、
お金
診察券(過去に通院の場合)
保険証
メガネ
サングラス
といったものが挙げられます。
メガネは視力の確認に使う場合があります。
サングラスについては散瞳薬の影響で屋外での行動が困難になるため持参してください。

散瞳検査の手順
散瞳検査の手順は以下のとおり。
散瞳薬(目薬)点眼
↓
15~20分ほど待機
↓
散瞳眼底カメラ等を使って検査
大まかな流れはこんな感じです。
症状や検査内容によって変わってくると思います。
検査での注意点
散瞳検査を受ける際(受けた際)にはいくつか注意すべき点があります。
検査前に以下の点について把握しておきましょう。

検査後は車やバイク、自転車の運転ができません
散瞳薬の効果は4~5時間ほど続きます。
これによる影響は、
・視界がぼやける
・晴天化で異常な眩しさを感じる
こういったことがありますので、自転車を含め運転と名の付く行為は出来ません。

サングラスは必須
屋外ではサングラスが必須と考えます。
薄暗い屋内でしたらそれほど眩しさを感じませんが、屋外ではとてもではありませんが周囲を見ることが出来ません。
眼が痛いと感じるほどです。

人によってはサングラスをしても眩しく感じるでしょう。
歩行の際も周囲を歩く人やちょっとした段差に注意が必要です。
また、サングラスはUVカットされているものが良いです。
メガネ店で売っているようなしっかりUVカット数値が表示されているものが良いと考えます。
一日仕事と考える
散瞳検査は一日仕事です。
検査自体は1時間もかかりませんが、散瞳薬の効果時間を考えるとほぼ一日何もできません。
ですから、眼科以外の予定は入れない方が良いです。
日常的な買い物ぐらいなら何とかなりますが、運転や細かい作業、危険を伴う作業は出来ないと考えておいてください。
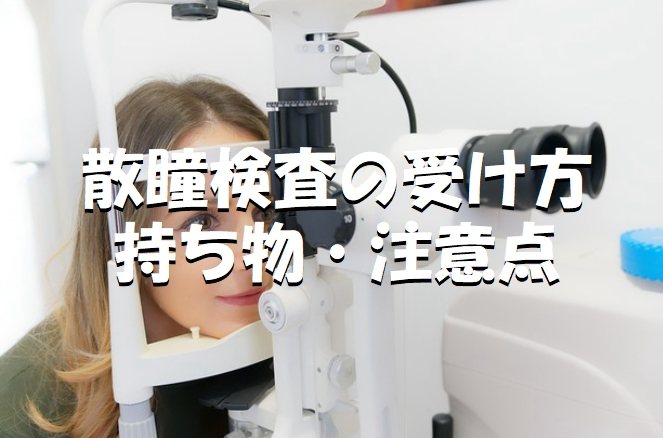
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/30243dd4.5791c9fb.30243dd5.4f8d3b9a/?me_id=1241201&item_id=10007693&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fjins-ec%2Fcabinet%2Fitem%2F202207%2Fmcf-19s-402.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)



コメント